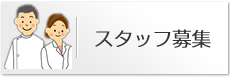テオフィリン製剤の副作用 急性脳炎(痙攣発作)
先日マスコミでぜんそく治療剤のテオフィリン製剤における急性脳炎が取り上げられていました。テオフィリン製剤の副作用で急性脳炎や痙攣は以前から知られており、痙攣を回避するために血中濃度モニタリングが重要です。しかし、小児においては、テオフィリンの血中濃度が治療域であっても発症することがあります。
テオフィリンの副作用として
大人では、嘔気、嘔吐などの消化器症状、頻脈、動悸などの循環器症状が多く、子供では興奮、傾眠、振戦などの神経系の副作用が多いです。これらは、薬の投与量が多いほど出現しやすい。しかし痙攣は血中濃度が低いときにも生じることがわかっています。
血中濃度は様々な因子の影響で上昇します。
年齢:6ヶ月未満、高齢者
薬剤:エリスロシン、クラリスなどの相互作用
肥満、インフルエンザワクチン、発熱など。
てんかんの既往歴のあるお子様をお持ちの保護者の方は主治医にその旨を話して下さい。
また、テオフィリン製剤を服用中に発熱した場合は主治医に服用の相談を行って下さい。
ここに示す小児の発熱時におけるテオフィリン製剤の服用例は、あくまでも目安であり自己判断で行うとぜんそく発作を誘引したりする場合がありますので、すべて主治医の指示に従って下さい。
てんかん及び痙攣の既往歴のある患者
→服用を中止し、解熱してから服用を再開する。
乳幼児(5歳以下)
→減量又は中止
→注意深く観察を行い、いつもと違うと感じたときは、服用を中止する。
これからの季節は発熱する場合が多くなります。テオフィリン製剤を服用している患者様、保護者の皆様はその場合に備えて主治医によく相談し、自己判断的な服用は避けるようご注意下さい。
医薬品副作用被害救済制度とは・・・
医薬品副作用被害救済制度をご存じですか?
○この制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づいた公的な制度です。
○医薬品は両刃の剣といわれるように有効性と安全性のバランスの上に成り立っているので、その使用に当たって十分な注意を払っても副作用が発生することがあります。
○医薬品を正しく使用したにもかかわらず入院を必要とする程度以上の副作用が起きた場合には、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金など副作用救済給付が行われています。
○副作用救済給付の請求については、当医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)へご相談下さい。
○制度の仕組みを解説したパンフレット及び請求用紙を無料でお送りします。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−3−2 新霞ヶ関ビル10階
℡ 0120−149−931(フリーダイアル)
℡ 03−3506−9411(携帯電話・公衆電話からのご利用)
http://www.pmda.go.jp/
E-mail kyufu@pmda.go.jp
医薬品副作用被害救済制度とは・・・
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が発生した場合に、医療費等の諸給付を行う法律に基づく公的制度です。
病院・診療所で投薬された医薬品や薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による健康障害が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の諸給付を行い、これにより、被害者の迅速な救済を図ろうとするのが、この制度です。
どの様な被害が対象となりますか・・・・
昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって、その使用が適正であったにもかかわらず発生した副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの)及び死亡です。なお、以下のような場合には、救済の対象となりません。
①法廷予防接種を受けたことによるものである場合。なお、任意の予防接種を受けたことによるものである場合は本制度の対象となります。(法的予防接種を受けたことによるものである場合は、別の公的救済制度があります)。
②医薬品の製造業者や販売業者など損害賠償の責任が明らかな場合。
③救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害で、その発生が予め認識されていた場合。
④がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって厚生労働大臣の指定するもの(対象除外医薬品)等による場合。
⑤医薬品救済のうち軽度な健康被害や医薬品の不適正な使用によるものである場合。
この他にも請求期限など一定の条件があります。詳しいことはお問い合わせ下さい。
請求の方法は・・・
副作用による健康被害を受けた本人や家族が請求書に診断書などの必要な書類を添えて、機構に直接行うようになっています。
(なお、制度を解説したパンフレット及び請求用紙を無料で送付いたします。)
機構に提出された請求書、診断書等をもとに、その健康被害が医薬品の副作用によるものであるかどうかなどについて、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)で審議され、厚生労働大臣の判定結果をもとに機構において副作用救済給付の支給の可否を決定します。
薬とつきあうために
薬ってなに?でも書きましたが、薬は使い方を間違えると効果以上に薬害の心配が出てきます。
ある治療ではその副作用を目的として使用する場合もありますが、多くの場合薬害は出現してもらっては困るものです。
では、どういう風に薬と付き合ったら薬害を出さずに薬と付き合うことが出来るのでしょうか?
○用法用量を守ってください。処方薬はその患者さんに合わせた量と服用回数が決められています。仕事が忙しくて早く治さないといけないからと言う理由で処方量の2倍服用して副作用が起きた事もあります。
○古い薬は飲まないで下さい。薬にも有効期限があります。きちんと管理された状態で約1〜2年(薬によって異なります)服用できますが、管理状態が悪かったり、散剤・水剤のように混ぜることによって有効期限はかなり短くなります。そんな古い薬を服用することで効果が出なかったり、副作用が出たりすることもあります。古くなった薬は近くの薬局に持って行って処分してもらって下さい。
○どんな薬であっても恋人、友人、家族、子供、いかなる人にでも自分の服用している薬を服用させないでください。処方薬はその患者さんにあわせて作られているものであって、その患者さんの家族や、友達に合わせて作っているわけではありません。体重も違えば薬物の代謝状態、薬の相性も違う場合があります。自分が飲んでみて調子の良かった薬を他の人にのませて発疹・呼吸困難の急性期のアレルギー反応が起きたらどうしますか?殺人犯になりますか?良かれと思ったことで逆に大変なことになることがあるので、決して自分の薬を人に分け与えないでください。また、この行為は薬事法違反にもなります。
それと、薬を子供の前で飲まないで下さい。小さい子供は何でも興味を示します。大人が飲んでいるオレンジや赤や青の薬がマーブルチョコレートに見えてしまいます。大人が服用する降圧剤、高脂血症治療剤、気管支拡張剤、抗ガン剤等を興味本位で服用してしまったらどうしますか。また、子供の手の届くところに薬を置かないで下さい。外用剤である気管支拡張剤の液を飲んでしまって心臓に負担をかけたり、消毒剤を飲んでしまったり、小さい子供はなんでも物を口の中に入れてしまいます。親のちょっとした気遣いで薬害が予防することが来ます。
薬ってなに?
ホームページを作り最初に書かないといけないことを忘れていました。
そもそも薬って何なの?何故薬があるの?薬って本当に良いものなの?
薬は病気を治したり、それ以上病気が進まないようにしたり、病気であるかないかを診断したりする場合に使用します。
すべての病気を治せるわけではないけれど、ある程度の症状を抑えたり、治癒させたりすることが出来るものです。
しかし多くの方はこの治療の良い効果(正作用)しか見ていません。
ちょっと強引かもしれませんが、薬→くすり→(逆から読むと)リスク→Risk(負担)と、薬には表の作用と背中合わせに裏の作用(副作用)があるということを忘れてはいけません。
薬はほとんどの方が飲めば効きます。当然ですよね、製薬会社の研究者が十数年もかけて研究して、臨床試験を行い、効果が認められたもだけが、薬として販売されるのですから。
主治医もその効果を期待して処方するわけだし、一般薬局の薬剤師もその効果を期待して医薬品を販売するんですから。
薬は自然のものではありません、そこら当たりに薬は転がっていませんよね。人間が手を加えてその物質だけを抽出したり製造したものです。そのよう薬の使い方を間違えたり、患者さんが自己的な使い方をしたらどうなると思いますか?体に対する負担(Risk)である副作用が牙をむいて襲いかかってきます。
副作用は薬物によって症状や出現頻度は違いますが、日本で販売されている医薬品に副作用のないものはないと思って間違いありません。
一般的に副作用がないと言われている漢方薬でさえ、使い方を間違えるとミオパチという筋肉痛を起こす可能性があります。
薬のおかげで健康になり平均寿命が延びたのも事実です。でも、その反対に副作用で苦しんだり命を落としたりされている方がいることを忘れないでください。
どんなに良いものでも使い方を間違えれば大変なことになります。
でも、薬は怖いからと言って主治医から処方された薬を服用しなければ、病気の進行を抑えることは出来ません。現在はインフォームドコンセントといって患者さんが納得した上で治療を行うということが義務づけられています。手術であれ薬物療法であれ少しでも疑問点があれば主治医に質問し、納得した上で治療を受けてください。
もし使い方など薬のことが解らなければ皆さんの自宅の近くにある薬局を訪ねて、そこにいる薬剤師に相談してください。そして薬を安全に使うため指導などを受けてください。
近くに薬局がなければ私宛にメールをいただければお答えいたします。
薬はかんだり、潰したりして飲んで良いの?
在宅患者さんの家族から「最近錠剤が上手く飲めないようなんですが、錠剤を砕いて飲ませたりして良いですか?」という質問がありました。
錠剤は見た感じ同じように見えますが、それぞれ特徴があります。
裸錠:薬の成分に添加物を加えて錠剤としたもの。
糖衣錠:薬の苦味や刺激を隠すために、主成分を砂糖で包んだものです。
口腔内崩壊錠:水無でも服用できる錠剤で、口の中に入ると5〜20秒ほどでラムネ菓子のように溶けて簡単に飲み込めます。他の薬同様に水で飲んでも効果は変わりません。
“水なしでどこでも飲める薬”として、今後ますます多くなるものと 思われます。
フィルムコーティング錠:薬の苦味や刺激隠すためや副作用を出にくくするために、主成分を薄い膜(フィルム)で覆ったものです。
フィルムコーティング錠の中には味を隠すだけではなく他の目的がある場合があります。
胃酸で分解されて効果をなくす薬や、胃の壁を傷 つけやすい薬は、胃内で溶けず腸内で溶ける性質のフィルムで覆います。(腸溶錠)
徐放性製剤(1日1回や2回の服用でゆっくり溶け出して効果が出るようにしている製剤)
裸錠・糖衣錠は仮に潰して服用しても味が苦かったりして服用しにくいだけですが、フィルムコーティング錠の中には腸溶錠や徐放性製剤のように潰すことで効果が無くなったり、薬が効きすぎて副作用が起きたりすることがあります。
基本的に錠剤を潰すことはしない方が良いと考えますが、錠剤が飲めない場合などは他の散剤に変えたり、他の方法を考えないといけない場合がありますので、気軽に主治医や薬剤師に声をかけてください。
同様にカプセルをバラしたり、カプセルや顆粒をかんだで服用することもやめてください。