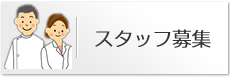漢方薬の飲み方
エキス顆粒剤・エキス錠(漢方薬をせんじて得たエキスを乾燥させ、顆粒剤または錠剤にしたものです)の飲み方として、添付文書には1日量を2~3回に分割し、食前又は食間に服用すると書いてあります。
漢方薬の風邪の症状に使われる薬で桂枝湯という漢方薬があります。この処方は傷寒論という本に載っていて、大塚敬節先生の書かれた解説書の中には薬を飲み終わって、ちょっとたってから熱いうすい粥を一合あまりすすって薬力を助けてやると良い。流れるように汗を出してはならない。かえって病が良くならない。もし一服で汗が出て良くなったらあとは飲む必要はない。もし、汗が出なかったらもう一度前のように飲むとよい。それでも汗が出なかったら、あとで飲む分は時間の間隔をつめて半日ばかりの間に。参服飲み尽くすようにする。と書かれています。
また、桂枝湯は熱い粥を食べて薬力を助けたが、麻黄湯は発刊力が強いのでその必要はない。と書かれています。
メーカーの添付文書はどれを見ても最初に示したようにしか書いてありませんが、本当の漢方薬はそれぞれによって使い方、捕食の取り方が違っています。
ご自分が飲んでいる漢方薬の飲み方について一度主治医・かかりつけの薬剤師さんの訪ねてみてはいかがでしょうか
どれくらい安くなるの
医療用医薬品の公定価格が定められており、それが薬価と呼ばれるものです。
薬価が低いほど患者さんの薬剤費の自己負担も軽くなります。
ジェネリック医薬品の薬価は新薬の7割(新発売時)と決められています。薬価は2年に1回見直されるため、発売時新薬の7割だったジェネリック医薬品もそれ以上価格差がつく場合があります。
負担軽減価格は使用される医薬品によって変わってきますが、ななしま薬局で対応した広域病院28日分処方において、負担金が約1000円軽減されました。年間で見ると12000円となりかなり大きな金額とは感じました。
軽減金額は薬剤によってかなり変わってきます。
7月に新しいジェネリック医薬品が発売されます。かかりつけ医・かかりつけ薬剤師に相談しては如何でしょうか?
薬を生活に合わせる
外来患者さんではあまり感じることはないのですが、在宅を行うとよく感じることがあります。特に高齢者の患者さんでは朝9時過ぎに起きて21時頃には就寝するという流れの中で食事を朝昼兼用にしていたりして、1日に2回しか食べていない患者さん。その患者さんに1日3回食後服用の薬が処方されていた場合、昼の薬はほとんど飲まないまま残っています。
生活時間と服薬時間のずれにより、患者さんが勝手な判断で朝や昼の薬を抜いたり、患者さんが混乱したりするパターンがあります。
その患者さんにどうして1日2回しか食べないため、1日3回の薬は飲めないことを伝えなかったのかと確認したところ、「言うとめんどくさい」「解ってもらえなかったから」等の答えが返ってきました。
これらの患者さんは主治医と話し合い薬の内容を見直し、1日2回の服用に変更しました。
服薬に生活を合わせるのではなく、生活に服薬を合わせなければならないのに、それが上手く行っていない現状に悲しくなりました。
病状や薬によってはできないこともありますが、どんなによい薬であってもそれを上手に使わないと薬は効果を出しません。
もし服薬時間が生活に合わない患者さんがおられましたら、遠慮なく主治医、かかりつけ薬剤師に相談してください。
我々薬剤師も薬の薬効とか副作用のことばかりではなく、その患者さんの生活リズムを知り、その生活にあった服薬スタイルを取れるよう主治医と検討していかなければいけないと感じます。
ジェネリック医薬品
| ジェネリック医薬品ってなに |
| 欧米では有効成分の一般名(generic name)で処方されることが多いため、それをとって「ジェネリック」という言葉で呼ばれています。 |
| ジェネリック医薬品って全く同じものなの? |
| ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬が承認発売され、再審査期間や特許の有効期間が過ぎてから製造販売されるものです。新薬と同じ有効成分で同じ含有量、効能・効果、用法・用量が同じであり、新薬に比べて低価格な医薬品です。 ただし、ジェネリック医薬品は主成分に関しては同じですが、それに付随する添加物、製法特許や製剤特許に関しては、薬品製造メーカーの特許が切れていないものもあり、ジェネリック医薬品によっては違う添加物を使用したり、新薬と違う作り方をしているものもあり、すべてが全く同じなコピー製品と言うわけではありません。 また、新薬の「用途特許」が存在する場合にはジェネリック医薬品で効能・効果が異なる場合がごくまれにあります。特許上の問題以外にも新薬の効能・効果あるいは剤型の追加等に伴って新たな再審査が設定されている場合も、適応症が異なる場合があります。 |
| 副作用の対応 |
| 医薬品副作用被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、先発医薬品、ジェネリック医薬品の区別なく適応されます。 |
| 処方箋様式の変更 |
| 2006年4月より処方箋様式が変更されました。備考欄に「後発医薬品の変更可」と記載したチェック欄が予め設けられるようになりました(処方箋の右下辺りにあります)。この欄に処方医が署名もしくは記名、捺印を行えば、薬局は患者の同意を得た上で先発医薬品をジェネリック医薬品に変更して調剤することが可能となります。しかしながら処方ごとに「変更不可」が記載されてあったり、ジェネリック医薬品が発売されていない医薬品においては、処方医のサインがあっても変更できません。 |
ジェネリック医薬品にするとどうなの? |
| ジェネリック医薬品にすると先発医薬品とほぼ同等のものが安価に処方してもらえることになります。 ジェネリック医薬品は先発医薬品の70%の薬価が設定されますし、これまでに発売されているものは、それぞれの薬価が設けられています。選ぶ医薬品でお支払いいただく価格が変更します。また、国の支払う医療費を抑えることもできます。 ジェネリック医薬品だけでも相当の数が存在し、たぶんすべてのジェネリック医薬品を取りそろえている薬局は数少ないと思います。また、あるジェネリック医薬品は流通が上手く行かず手配するのに数日から数週間要するものもあります。 ジェネリック医薬品を希望される患者様がおられましたら、かかりつけの薬局でその有用性、価格、在庫等を良く相談の上、変更されることをお勧めいたします。 |
坐薬
坐剤はラテン語のsuppositriumからきた名称です。エジプトにあるエルベス古文書には、紀元前1500年頃に薬物が、坐薬として直腸に適用されていたという記録が残されており、坐剤が初めて使用されたのは、紀元前2600年頃の古代エジプト・メソポタミアにおいてだそうです。当時の坐剤は現在のような形状ではなく、動物性脂肪に薬を溶かし、羊毛に吸着させたタンポンのようなものであったとされています。
現在はヨーロッパを初め多くの国で使用されています。日本でも明治時代以後使用されはじめ、数多くの坐薬が子どもから大人まで使用されています。
私が初めて病院に勤めた頃(昭和63年)の笑い話に、1週間前に痛み止めの坐薬が処方されたおばあちゃんがいました。再来時に坐薬の効果を確認したところ、「よく効いたよ」と言われ安心したのもつかの間、「よく効いたけど、あの薬は大きいし脂っこいね〜べたべたしたからみそ汁に入れて飲んだよ」と言われました。おばあちゃんは坐薬・・・座って飲む薬と勘違いされたらしく、食後に座って坐薬を口の中に入れたらべらべらしたので、ぞれが嫌でみそ汁に溶かして座って飲んでいたとのことでした。今でこそ笑いながら話せることですが、坐薬だから一般的に肛門から入れるものと知っているだろうと思いこみこんな失敗をしてしまいました。
ある方からは坐薬の包装を剥かずにそのまま肛門に入れたと言う話を聞いたことがあります。
坐薬は、肛門や膣に入れる固形の薬です。坐薬は痔などの局所・鎮痛に使われるほか、直腸から薬を吸収させ炎症、嘔吐、痛み、熱発などの疾患にも使われています。これらの坐薬は、飲み薬と違い胃腸障害が少なく、食事に関係なくいつでも使えます。また、効き目が速いため、屯用としてよく処方されます。
「解熱と吐き気止めの坐薬を二種類もらいました。どのくらいの間隔をあけて使用すればよいでしょうか?」「抗生剤の坐薬と熱冷ましの坐薬」「痙攣止めと解熱剤の坐薬」という患者様からの質問がありました。
坐薬はお子様の場合2種類、3種類と処方される場合があります。それではどの坐薬からどの様な順番で使用するのが良いのかは、効果の違う坐薬を同時間帯に使用する場合、基剤(薬の成分を溶かしているもの、水溶性と油脂性があります)の違いによってそれぞれの吸収が遅くなったり、吸収できなかったりして期待する効果を得られない場合があります。違う坐薬を同時間帯に使いたい場合は、30分以上間隔をあけて挿入しましょう。
例として
①ナウゼリン坐薬(水溶性基剤-成分は脂溶性物質)とアンヒバ・アルピニー・カロナールなどの解熱坐剤(油脂性基剤)の場合、ナウゼリン坐薬を先に入れて、30分以上経ってから解熱の坐薬を挿入します。
基本的に冷蔵庫で保管される坐薬は油脂性基剤、室温で保管されるものは水溶性基剤と考えて良いでしょう。
②熱性けいれん予防でダイアップ坐薬(けいれん止め・予防)を使用している場合、けいれんを起こさないことが先決なので、まず最初にダイアップ坐薬を使用して30分あけて、他の坐薬を使用してください。