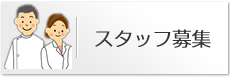薬剤師と在宅医療
日本薬学会のホームページに昭和薬科大学 串田一樹先生が「在宅医療の進展と薬剤師」という項目で掲載されていました。いろんな意味で考えさせられる内容でしたので皆様に読んでいただきたくて掲載させていただきます。
「高齢社会の到来によって医療提供のあり方も変化し、その中でも医療の機能分化が進み、従来は入院せざるを得なかった医療依存度の高い患者さんが居宅で療養できるようになってきた。最近では、在宅医療の進歩に寄与するような新薬の開発も行われており、一例を挙げると、2002年に我が国で承認された麻薬性鎮痛剤フェンタニルの貼付剤は皮膚から吸収されて持続的に全身に作用するものであり、経口モルヒネ剤の服用が困難ながん患者でも注射によらない疼痛コントロールが可能となったことから、在宅医療の可能性が大きく広がっている。在宅医療の進展に伴い、薬剤師が居宅を訪問して薬剤の管理や指導を行うことも重要な業務となり、薬物療法全般について臨床判断が求められるとともに、患者、家族や他の医療職とのコミュニケーションも不可欠になっている。薬剤師は在宅医療を担うという観点からも、これまでよりさらに高い資質が求められる新たな時代を迎えた。」
今年の4月に医療法改正が行われ薬局の診療報酬も在宅医療を行う方向で傾いてきているのも事実のようです。いままで、温室の中で育ってきた薬剤師がどうのような形で在宅に関与していくのかすごく不安に感じます。私も在宅を始めて11年目に入りましたが、もう一度いろんな面で在宅医療の見直しを
行ってみようと思います。
血圧と塩
食塩の取りすぎは血圧を上げると言われています。どうして食塩を取りすぎると血圧が上がるのでしょうか?
塩を食べるとしょっぱくて、たくさん食べるとのどが渇きますよね。のどが渇くと水を欲しくなりますよね。それが、体の中で起きていると考えてください。
体の中に多くの塩分がとり込まれると、血液中の塩分の濃度が高くなり、体がこれを薄めようと作用します。このために血管中に水が取り入れられ、高くなった塩分の濃度を薄めることになります。血管の中に水分が入ると、全体の血液量が増えるので心臓に負担をかけたり、むくみの原因の1つとなったりします。
医師や栄養士さんが塩分を控えるように話すのはそのためです。
薬で血圧を下げようとしても、食生活が上手くできていない状態なら効果も上がらない可能性があります。
健康な人でも1日に10g以下を目標にしてください。高血圧、心疾患のある人は医師から指示された塩分量(一般に7g以下)を守って下さい。
漢方薬の副作用
漢方薬に副作用はないのですかとよく質問を受けます。漢方薬に元来副作用という概念はなく、もし副作用が出たらそれは誤治(診断ミスか投薬ミス)とされています。
しかし漢方エキス製剤には副作用の項目があり、西洋薬ほどではないけれど副作用が記載されています。
多くの方が肩こりに葛根湯を服薬しますが、葛根湯は傷寒論では表実証の薬として分類されています。この葛根湯を体力の落ちた状態の方が服薬したらむかむかしたり、体がだるくなったりすることがあります。これを副作用とするか誤治とするかの違いになると思います。
また、漢方では猛毒を持つトリカブト(附子)も体を温める効果のある生薬として使用しますが、ちゃんとその毒の抜き方(焙じ)を行っています。しかし、そんな附子製剤の入った薬を体が冷えるからと行って体格の良い方が服薬したら心臓はばくばくなったり、のぼせたりして大変なことになります。これも先ほどと同じように副作用とするか誤治とするかの違いになると思います。
もし、薬局で漢方薬を購入する際は病気から漢方薬を選ぶのではなく自分の体のことをきちんと話して漢方薬の選択を行ってください。そうしないと副作用を起こすことになりますよ。
在宅
患者さんの家に訪問をするようになって気づいたらもう10年過ぎていました。
今日は今までの中でも少し切なくなったので、少し気持ちを書いてみたいと思います。
昨日、訪問の処方元の先生より、12月に入院した患者さんが危篤になったという連絡を受けましたが、どうしてもしなければ行けない事があったので見舞いに行くことが出来ませんでした。
今日、朝から患者さん宅を回る予定があったのと、先日亡くなった患者さん宅を訪問する予定があったのでお見舞いに行ってきました。
定期訪問の患者さんは落ち着いておられ、約3時間で5名の患者さん宅を回り、途中で1月に亡くなられた患者さん宅にご焼香に訪問しました。
一ヶ月ぶりにご家族の方とお会いしました。ご家族の方はあのまま、自宅で見ていた方が良かったのじゃなかろうか、本当に入院させたことが良かったのだろうか
漢方薬の飲み方
エキス顆粒剤・エキス錠(漢方薬をせんじて得たエキスを乾燥させ、顆粒剤または錠剤にしたものです)の飲み方として、添付文書には1日量を2~3回に分割し、食前又は食間に服用すると書いてあります。
漢方薬の風邪の症状に使われる薬で桂枝湯という漢方薬があります。この処方は傷寒論という本に載っていて、大塚敬節先生の書かれた解説書の中には薬を飲み終わって、ちょっとたってから熱いうすい粥を一合あまりすすって薬力を助けてやると良い。流れるように汗を出してはならない。かえって病が良くならない。もし一服で汗が出て良くなったらあとは飲む必要はない。もし、汗が出なかったらもう一度前のように飲むとよい。それでも汗が出なかったら、あとで飲む分は時間の間隔をつめて半日ばかりの間に。参服飲み尽くすようにする。と書かれています。
また、桂枝湯は熱い粥を食べて薬力を助けたが、麻黄湯は発刊力が強いのでその必要はない。と書かれています。
メーカーの添付文書はどれを見ても最初に示したようにしか書いてありませんが、本当の漢方薬はそれぞれによって使い方、捕食の取り方が違っています。
ご自分が飲んでいる漢方薬の飲み方について一度主治医・かかりつけの薬剤師さんの訪ねてみてはいかがでしょうか